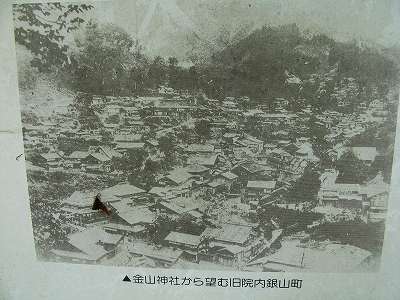2007年8月カブでのろのろ・・・再び東北へ。(前編)
また吸い寄せられるように東北へと向かいます。昨年と違うのは、cub君が進化?し、ちょっと大型になったこと。
今回の大まかなプラン。
一日目秋田港から南下、象潟を経て、金山の町並。そして、山形県新庄近くの瀬見温泉に投宿。二日目。北上し、大曲泊。たぶん雨でもみくちゃ。三日目。弘前でねぷた祭り。四日目。五所川原でこれまた立ちねぷた。それからは未定。8日朝に秋田港からフェリーで戻ります。気になるのは台風。既に九州方面に影響を与えています。ウサギという名前が付いているのだとか。天気予報では番号でしか呼びませんが、太平洋の周辺諸国の言葉を順繰りに回して命名しているそうですよ。で、今回は日本語の名前でウサギ。日本の命名はすべて星座の名前を当てているそう。だから、コップとか、ふたごとかやぎとかそんんな名前がつきます。ちょっとさえない気もしますが、まあ目くじらを立てるほどの大問題でもない。ぜんたいほとんど知られてないですし。
今回は、夏用のライディングジャケットを着ての出発。まあ、安心のため。これ、肩や肘や背骨のあたりには分厚い樹脂製のパッドが入ってます。ひざにもプラスチックのガードをはめて万全。外からは見えません。重装備ながらメッシュでできているため走っている限りは風が通り、快適とは言えないまでも、汗でどろどろになることはありません。渋滞になると最低ですけれど。
では出発です。
その昔、若狭湾で捕れた鯖を京都まで運んだという鯖街道をさかのぼるcub君。昔は徒歩で数日かかったのがcub君でも2時間かからないでしょう。あっと言う間です。小浜で塩をした鯖がほどよくなれた距離だといいますが、これではまだ新しいうちに着いてしまいます。
三千院で名高い大原を過ぎ、山の中を北上します。山に入ると急に雲が厚く、そしてどんより鈍色に変わります。おいおい、明日あさっては覚悟しているけど、ここからもう雨かい。路面はびっしょり濡れて、風に揺られた木の枝からは大きな水滴が降ってきます。さいさきの悪いことといったら。
琵琶湖の西に位置する山間の町、旧朽木村がずっとそんな感じでした。これはもう来るな、と思ったところでちょうど下界へ。なんでしょうね。嘘のような快晴です。ここから順調。

敦賀港のcub君

そして秋田まで一緒、フェリーアザレア

しばらくここでがまんのカブ君。
乗り場では炎天下随分待たされて、汗びっしょりになってやっと乗船です。乗車完了後すぐ出航。定刻10時。
さっさとすいている風呂に入って、ビールを飲みながら音楽を聴きながらちょっと疲れたら海を見ながら・・・本を読みます。贅沢。時折やってくる眠気に身を任せてとろとろ。起きるとまた読書。夕方までそんな調子で過ごします。なんたって眠いのをこらえて頑張る必要がないのがいいですね。

ゆったり船旅。
夕方になると、今度は晩ごはん用に買っておいたコンビニの弁当をさかなに、同じ場所に陣取って酒をちびちび飲みながらまた読書。
水上勉が書いた、一休の伝記を読んでます。破戒ぶりが徹底していて胸がすくような思いです。戒律そのものがすでに人間によって作り出された迷妄だといったところなんでしょうか。徹底的な自由さが当時の御用仏教と相いれない様子に、決して多くない原資料から、水上勉が執念で迫っていきます。資料がそのまま引用されているので読みにくいことこのうえない。特に、禅の境地を漢詩に詠んだものはもうお手上げ。
酔いが回ってきてこっちの頭も自由奔放に、てんで勝手な方向に働き始めたので、寝台に戻って寝ることにします。
夜10時。静かになったと思ったら新潟に入港。
台風(アジア名ウサギ)は宮崎に上陸したと、ニュースが伝えています。まだこっちは全然影響ないですが、大丈夫でしょうか?

午後のもの憂い一時。
早朝5時秋田港接岸。
国道7号線を南下開始。大体一桁台の国道って、面白くないんですよね。ここも車が多くてみんなとばすから遠慮がちに走ります。左に寄ってどんどん先に行かせます。
途中道の駅で朝食。昨日フェリーで夕食を早く食べたため、売店が閉まっておなかがすいてはいかんと買っておいた、あんぱんと缶コーヒー。波の音を聞きながらまずいまずいパンをほお張ります。でも、日本海を前にしてカブ君と食べる朝食はとってもきもちがいい。

cub君と朝食の図。
心配していた台風はまだこっちの方までは影響を及ぼしてないようです。そのかわり暑い暑い。例の新しいジャケットは風を通すものの色はあまり目立たないように黒。信号で停まったとたんにどっと汗が吹き出します。とにかくひたすら暑さに耐えて象潟到着。まえから一度見たいと思っていた場所。宮城の松島と並び称された海に浮かぶ島々が、1807年の象潟地震で生じた土地の隆起によって島ではなくなってしまったという場所。奥の細道にも「象潟は恨むがごとし」と出てきますが、近づくにつれて興奮してきます。駅で散歩マップをもらい、cub君で回ります。
おお、なるほどなるほど。島です。たしかに。稲の海に松の密生した小高い島のような場所が転々と。ちょうど自転車で昔海だった畑にやってきたおばさん、目だけ出して顔の上半分を真っ黒い布で覆う「ふくべ」(っていったと思う)姿で農作業を始めます。実物を見られると思ってはいなかった。こりゃうれしい。
たんぼとたんぼの間の畦をちょっと広げたような道を、cub君でぐるぐるまわりながら、景色を楽しみます。鳥海山が目の前に迫って、これも雄大な借景になります。


田圃の海に浮かぶ島々
芭蕉が寄った、蚶満寺へも。ここが島だった証しに、船をつなぐ石がいまでも残っていますね。ここの木々はきちんと手入れされていて、特に表にあるのはそのまま盆栽にしてもおかしくないようなもの。そして、鐘楼のきわには大きく茂る芭蕉が。真っ黒な瓦が敷き詰められた大きく、なだらかな建物の屋根と、芭蕉の取り合わせ。東北にいることを忘れるような不思議な感覚に襲われます。

蚶満寺の芭蕉。
裏庭に回ると、さきほどの船をつなぐ石のほかに、親鸞聖人が腰掛けた石。(なんと江戸時代に九州島原のお寺から移されたとは。どのような力がこんな大きな石を運ばせたのか。)木登り地蔵といって、大きなタブの木の、二股に分かれているところにひっそりとお地蔵さんがいて上からこちらを見てらっしゃる。

木登り地蔵さま

裏庭での一こま
もっといろいろ由緒あるものが並んでいるんですが、風景に目を奪われる私。この裏庭から昔の海を見渡すと、一面の稲の海に島がぽつぽつ浮かんでいて、水の上じゃあなくったってこれは日本三景に負けないでしょう。太鼓判を押します。

いやあおもしろいです、このお寺。おもしろいったって、もちろんがははと大笑いするようなのじゃあないんですが、私ごのみ。まだ朝早いからほとんど人もいないし、こんな風景を独り占めできるのはたいそう贅沢ですなあ。
どんどん汗くさくなってくる体とはうらはらに精神は飛翔してゆきます。しすぎるとアブナイけど。
さあつぎつぎ!まだ9時過ぎたところです。cub君の鼻先を県道58号線へ向けて。これで鳥海山麓をぐるりとまわって、内陸部へ入り込みます。そして、国道7号線から別れたとたん。もっと精神は飛翔を開始。どんどん山の方になだらかに入っていく道はほとんど車も通らず、途中青少年センターみたいなところを過ぎたとたんに狭くなったけれど、これぞツーリングの醍醐味というべき一級の道でした。

県道58号線から日本海を眺める

県道58号沿いにある「駒の王子」(由緒はわかりません)
大自然の中、どんどん標高が上がって行き、急なカーブで車体を傾けてカーブの先を見る目に、一瞬だけ、見渡す限りの森の先に波が光っているのが見える。もしかすると波なんて見えないかもしれないのに、脳裏にはきっちりと波の映像が焼き付いています。この県道58号が矢島で終わると今度は国道108号線。
矢島は、日本海側の羽後本荘から伸びてきた、由利高原鉄道鳥海山ろく線の終点。駅好きの私は、もちろん矢島駅に直行。JRから第3セクターになってきれいに建て替えられている様子。隣に、どう見ても駅の形をした古くてちっちゃい建物が残ってますから。本当なら、この線はずっと山を越えてかまくらで有名な横手までつながれる予定だったと、どこかで読んだことがあります。横手側からも線路が伸びてきていたそうですが、二つの線路が出会うことはなく、横手側の方はもう随分前に廃止されてしまいました。で、今はこの線は行き止まり。探してみると、こんなふうに両側から伸びてきて完成する前に工事が中断したところって、あちこちにあるんですね。
福井から九頭竜湖までの越美北線。これは、山を越えて美濃太田までつながる予定でした。ところが山間部だけ残してつながっていない状態で、これまた工事は中断。南の方、岐阜側は第3セクター長良川鉄道となっています。その他、九州や四国やまあ、あっちこっちにありますね。北海道なんかだと、すでに両側ともに廃止されていて、跡形もない場所があります。道路なんかだと、これから作られていくものというのが当たり前になっていますが、鉄道の網目はもうこれから都市部以外にはそうそう広がることがないでしょうから、完成せずに忘れ去られていく・・・というところが私の心をとらえてしまうんです。

矢島駅。木造でかわいらしい。
日本各地でこういった路線の工事が進むなか、モータリゼーションの波が日本に押し寄せ、それにともなってローカル線の乗客がどんどん減り、打ち捨てられていった区間と言えるでしょう。そして、国鉄がJRに変わって、残った路線もJRから見捨てられて第3セクターになっているところが多い。まあ、仕方のない部分もあるでしょうが、寂しい感じは否めません。
あらあら、話がそれてしまいました。国道108号線でした。
風景はさっきの道にどうしても負けてしまうけれど、車が少ないのがなによりいいですね。快調に南下。途中でこんなすばらいいおうちを発見。

山間部に入ると国道とは言えだいぶ道が狭くなります。で、「右 院内銀山跡」の標識。いちどはやり過ごしたんですが、去年もこうやってUターンして見た岩手県の玉川鉱山で楽しんだ記憶が頭をかすめ、だいぶ戻って脇道へそれます。いやあここもすごかった。私以外に一組だけ訪れる人がいましたが、ここはもうすでに「跡」でした。廃墟ですらない。
例えば、開国してから近代化のために外国人を呼び、彼らのために洋風の家を建てた異人館跡。苔むした石段だけが少し高くなった場所へ続き、建物があったとおぼしき場所はもう一面の草、草、草。足を踏み入れることができない程のおびただしい草に覆われています。

階段だけが残る。

明治天皇がの行幸があった旧坑道
そのなかで一番心を捉えてはなさなかったのは、墓地です。17世紀に発見され、天保のころにはなんと久保田城下(今の秋田市)以上の人口を誇った銀山であってみれば(なんと一万五千人もの人々がここに暮らしていたらしい!)、ここで産まれ育ち亡くなっていった人も多い訳で、それらの人達がここに葬られているんです。坑道があった場所より随分手前、おびただしい古い墓石が並ぶ姿は圧巻です。地形の起伏にしたがって、小さな墓石が多いですが、ずらりと並んでいる。みんなそれぞれの人生を全うして、あるいは全うできないままこの場所に静かに眠っています。それぞれがそれぞれの人生を送ってそして人生を終えたわけですね。誰ひとりとして同じではない人生を。手を合わせた後で写真を一枚だけ撮らせていただきました。

お寺もいくつかあったようで、全く跡形もなくなっているもの、鐘付堂は残っているものといろいろです。神社はそのままの姿で残っていました。

鐘楼だけが残っている。
細いメインルートにしたがってどんどん奥まで入れますが、辺りに人影はなく、草ぼうぼうで、いったいどこにそれだけの人が暮らしていたのか、想像することすら困難です。
「夏草や兵どもが夢の跡」の句を得た芭蕉は、平泉の草はらをこんな思いで眺めていたのでしょうか。
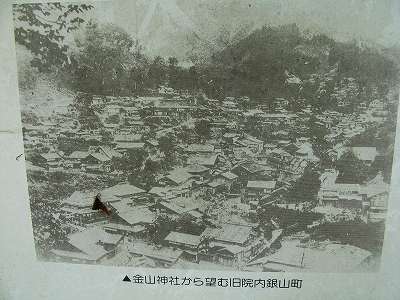
案内板にあった、往時の写真。今は草と木ばかり。
ここでかなりの時間を費やしてしまい、だんだんお腹がすいてきます(笑)で、金山を目指して南下開始。
その前に金山に行く途中にある、この駅名何と読むでしょう?答えはこのページの最後に。

これは難読駅名でしょう。
金山はその昔明治時代に、英国の作家イサベルバード女史が褒めたたえた町。彼女の「日本奥地紀行」には「ロマンチック」な風景だと描かれています。人々が親切だとも。
このところ、町作りを100年のスパンで考えていこうという試みが、あちらこちらで紹介されるようになりました。それででしょうか、最近、この街自体も紹介される機会が増えています。
この町を歩いてすぐ、落ち着くというかほっとするというそんな感覚に捉えられます。たまたま入った蕎麦屋「草々」でその話をすると、この町は景観を守るために、いろいろなことをしているのだとか。百年先を見据えて考えている。お蕎麦屋の奥さんが言うには、自分の家も屋根は違った色のトタンだったけれど、茶色に塗り直した。茶色にすれば少しだけれど町から補助金がおりる。新築の時もこの町の定める様式を守って普請すれば、いくばくかの補助が降りるそうです。で、そのあと町をちょっとだけですが歩いて驚いたのは、歴史的な建築はもとより普通の家や商店も落ち着いた茶と白系統で統一されており、そのためにほっとしたんだと思われます。それは何も和風建築に限りません。銀行もしかり、車屋さんもほかの町じゃあ絶対にこんな地味ではないという外見です。看板なんかは特に規制している訳ではないけれど、自主的にみんなが落ち着いた風合いのものにしていっているようです。ただ、看板は目立たせるものなのに、そんなふうでいいのかとも思うとか。

薬屋さん。

車屋さん。信じられないでしょう。街の風景にとけ込んでいます。
町の人も町のことを誇りに思っているようで、お蕎麦の奥さんもそうだし、役場の近くで地図を見ていたら、金山を回るんだったらあそこにパンフレットがあるよと、わざわざ教えてくれたおじいさんからも、町への誇りを感じました。
それと付け加えみたいになってしまいましたが、この蕎麦、ご主人がJRを退職されてから打つようになったとは信じられないほど、おいしいものでした。

おいしかった鶏そば。

たまたまみつけた蕎麦屋「草々」
この明治時代に建った家は、昼間ソバ屋をやっている時だけ借りているのだそうな。どうりで奥さんが他人事のように家のことを語る訳です。ここはこの町の名家のようで、ちょうど太宰治の生家、斜陽館に作り方が似ているように思います。玄関を入ると、細長い土間がずうっと奥まで通じ、左手に部屋が並ぶという構造。なんと、先々代の自家用人力車が飾ってありました。自家用とは驚きです。天井の高い座敷でおいしいそばとおしゃべりを堪能しました。

自家用人力車
さて、ここから今日の宿、瀬見温泉まではそうありません。3時過にチェックインして、明日の天気をみると、完全に雨。なら、しょうがない。明日訪れる予定だった、芭蕉が泊まった家がそのまま残っているという封人の家、そしてこれまた以前からずっと行きたくて仕様がなかった堺田の分水嶺。今日のうちに見に行きました。場所的には、今日の宿泊地、瀬見温泉から宮城県の方に15キロばかり行ったところ、名前から分かるように県境、昔の国境です。
封人の家は300年ほど前の庄屋の家で、建坪が80坪もあり、茅葺きです。入り口を入ると広い土間。右側には馬の部屋が並び、左側に人間の住居。この家に芭蕉は数日滞在し、有名な「蚤しらみうまの尿する枕元」の句をを得たのです。まあ、芭蕉たちが泊まったのはまさか馬小屋ではないでしょうから本当に枕元にうまの尿が降ってきた訳ではないでしょうが、いろりを切ってある板敷きの居間に座ると、土間の向こうには馬がこっち向いて立っている訳で、息遣いなんかははっきり聞こえたでしょう。むしろ、動物と一つ屋根の下にに暮らすということが新しい発見だったのではないか。その発見があの句に結晶したのではないかと、実際にここに来てみてそう思ったことでした。
 これは芭蕉が泊まったと思われる部屋。ふすまを開けると土間を通して馬の顔が見えます。
これは芭蕉が泊まったと思われる部屋。ふすまを開けると土間を通して馬の顔が見えます。

土間を通して玄関の方を見る。右奥に馬が見えますでしょうか。(人形だけど)

外から見た「封人の家」
ここから歩くこと数分、いよいよ分水嶺です。分水嶺までは、きれいに舗道が整備されていて、せせらぎの音、秋の虫の鳴き声、日暮らしの合唱。ぐるりは草地でいろんな花が咲いています。特に宮城県の方面を眺めやると、ずうっと続く草の波が果てるところは山。すばらしい場所です。分水嶺は、流れ出した用水が左右に分かれるその場所です。なにげない用水ですが、東に流れた水は太平洋へ、西に流れた水は日本海へ、もはや出会うことはないのです。目の前でどんどん二手に分かれて流れ出て行く水をじっとみつめます。目の前で分かれるというのが感慨深いですね。山を越えると川の向きが逆になっているというのはよく経験しますけどね。
下の写真は、分水嶺までの風景。


そして目の前で水が二手に別れて行きます。

これで今日一日旅を堪能したあとは、宿でひとりローソン弁当の包みを開けるのでした。
番外編 今日見つけた看板。不気味度ナンバーワン。しかもこんなの運転しながら読んで意味を考えていたらもう大変でしょう。魂まで飛翔してしまいます。

駅名の読み方答え。「のぞき」です。大阪の放出(はなてん)などとともに超がつく難読駅名でしょう。

後編へ続く カブの旅に戻る HOME